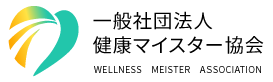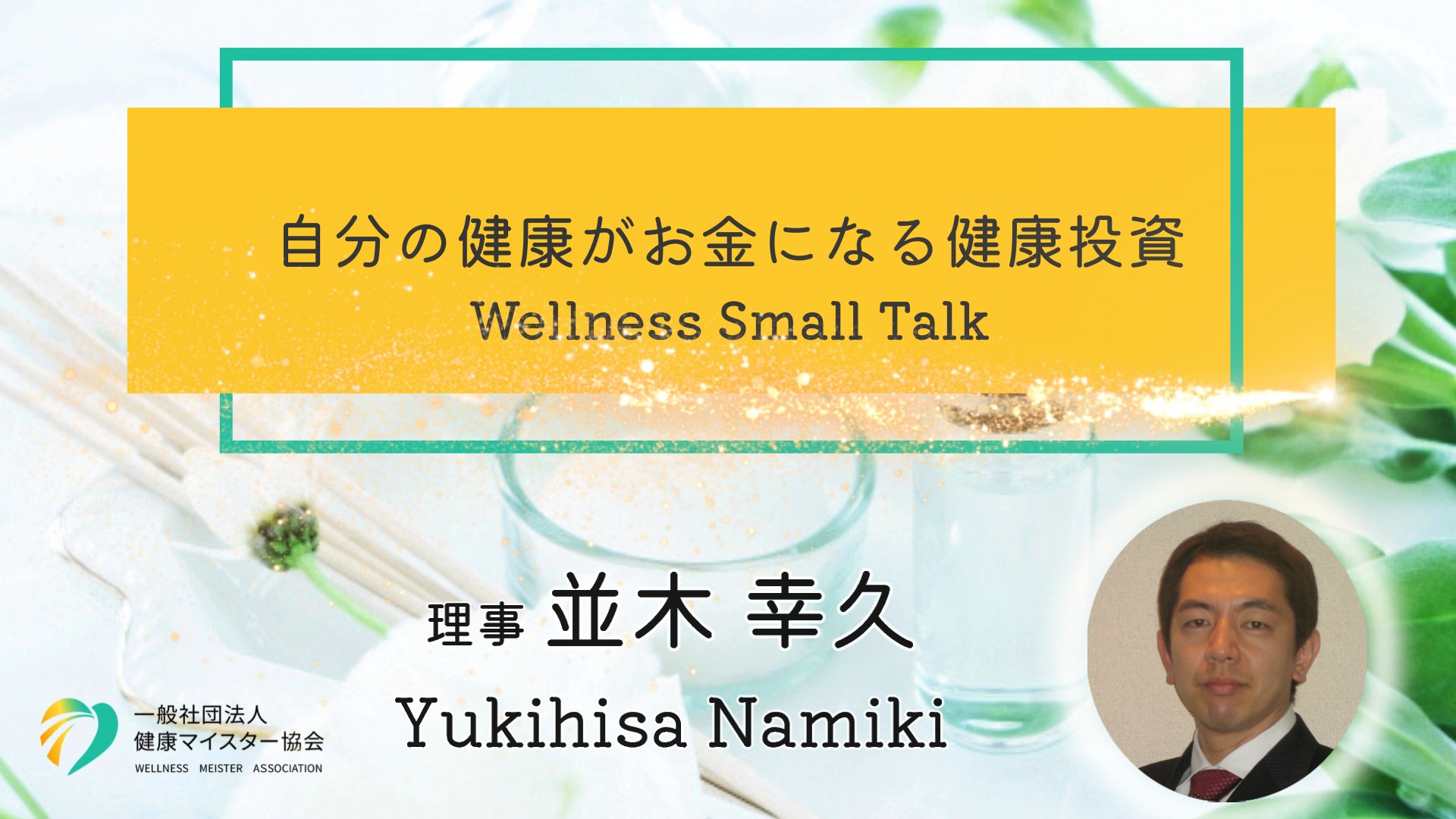もしも貴方の健康がお金になるならどうしますか?
お金と健康には密接な関係があるもののその関係が分かり難いために多くの人はお金を損しているのです。多くの人は働くことによりお金(収入)を得ますが、健康を損なうとこの収入が減ることはイメージしやすいですね。ただ、失う健康の量と減るお金の量の関係を計算することができないので、働くと得られるはずの収入が働けないことにより得られなくなる機会損失が生まれてしまいます。また、病気になるとその治療やお薬にお金が必要となります。つまり、お金を得ても支出が加わるので、使えるお金が減るのです。この無駄な支出を減らすことができれば使えるお金が増えるのと同じ関係ではあるものの多くの人は支払うお金よりも得られるお金に対して意識が働きやすいようです。会社の経営においても売上を作ることも大切なのですが、会社のコストを減らすことで会社の健全度が改善されることがありますが、コストが会社の収益を上回ると会社は潰れてしまいます。
病気になると将来得られるかも知れないお金が減るリスクや支出が増えることはイメージしやすいと思いますが、自分の健康自体がお金になることはあるのでしょうか?
ここでポイントになるのは、あなたは健康なのでしょうか?この問いに対して明確に回答するのは難しいものの、多くの人は「健康だと思います」とか「体調があまり良くないです」のような回答が多い印象です。何を基準に自分は健康と定義したら良いのか不明瞭なので自分の健康を計るための物差しが必要になります。日本肥満学会では、身長と体重から計算できるBMI(Body Mass Index)の値が18.5~25未満であれば適正体重(標準体重)とし、統計的に最も病気になりにくい体重と定義し、25以上を肥満、18.5未満を低体重と分類しています。ところが、BMIの計算方法は世界共通であるものの肥満の判定基準は国によって異なり、WHO(世界保健機構)の基準では30以上を肥満と定義しています。この他、SF-36(36-Item Short Form Health Survey)は36問の質問に選択肢から回答すると今の貴方の生活の質(QOL)を計ることができます。どちらの基準値も貴方の健康を直接計測できる指標ではないものの貴方の健康度についてヒントを与えてくれます。万能な健康の定義は難しい一方で、日本肥満学会が定める標準体重でSF-36の社会生活機能値が満点の人を対象とした健康を定義することもできます。
健康の定義は条件や基準を設けることで分類することができて、各条件や基準に応じた指導や対策を講じることができます。実はこの指導や対策はお金と密接な関係があるのです。表1には人データを利活用したビジネスを行っている東京証券取引所に上場している企業4社の事業、利活用しているデータ、売上高(2023年度)を会社四季報から引用してまとめました。これらの企業は一例ですが、人に関わるデータを利活用することで収益を作ることができているのです。貴方の個人情報が売買されている訳ではありませんが間接的または分析された人のデータが二次利用・三次利用など副次的に利用されることでお金が取引される経済価値になるのです。
| JMDC | MDV | エムスリー | メドピア | |
| 事業 | 健康保険組合の医療データを匿名加工し製薬・保険会社等へ提供。オムロンが筆頭株主 | 医療機関、製薬向けに医療・医薬品データのネットワーク化と利活用の両サービスを提供 | ソニーG関連会社。医療従事者向け情報サイトで製薬会社の情報提供支援。治験等周辺分野開拓 | 医師向け情報サイト運営、製薬会社の広告料が収益源。法人向け医療相談や特定保健指導も展開 |
| 利活用 データ | 健康保険組合の医療データを匿名加工 | 医療・医薬品データのネットワーク化と利活用 | 製薬会社の情報提供支援 | 医師向け情報 |
| 売上高 23年度 | 27,809百万円 | 6,419百万円 | 230,818百万円 | 14,540百万円 |
貴方が自分の健康を維持することは企業活動や第三者の健康作りに役立ちます。日本では少子高齢化により労働者の数が年々不足し、健康を損なうことで働けなくなる人は自分への損失だけでなく、日本社会にも不利益になるのです。つまり国民一人一人が自分の健康を維持して働くことができる仕組みは日本の社会保障システムになるのです。貴方のデータが年金のように積立てることができて、貴方のデータが第三者の健康作りに利活用されたり社会に役立てられたりした場合にお金を受取ることができれば第三の社会保障システムになるかも知れません。現在は一部の企業が貴方のデータを副次的に利活用することで収益を作れていますが、国民が自分の健康データから収益を得られる仕組みができれば健康投資が株式投資のように取引されるようになる新しい経済が日本から生まれるかも知れません。次回の予防経済コラムでは社員のメンタルヘルスを題材に、企業の健康投資について考えてみたいと思います。
アーカイブ動画はこちら